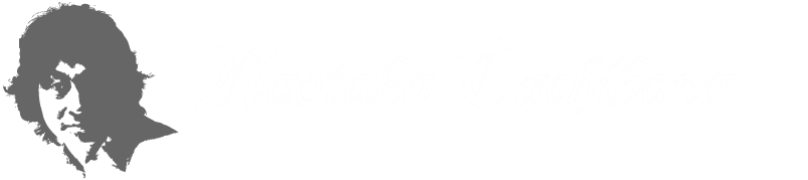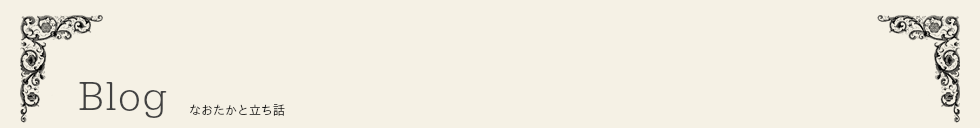今年もこうしてジャパン・スーパーユース・マンドリンオーケストラ(以下 JSYMO)が無事に開催できることを嬉しく、そしてたいへんありがたく思っています。
私が何故マンドリンの世界にこれだけ入れ込むのかと自分でも不思議に思うことがあります。それはこの世界には「まだ確立されていない何か」があるからではないかと思っています。
例えば私は小さい頃よりピアノを習っていました。先生から「今度○○をやるから、◯◯版の楽譜を買ってきてね」とよく言われたものです。
指揮者になってからは、オーケストラでの演目が決まると楽団からは必ず「何版を使いますか?」と聞かれます。その楽譜は売り譜としてあるものなのか、はたまたレンタルなのか、レンタルならばプロが使うのかアマチュアが借りるのかによって料金と借りる期間が違ってきます。最近はこれにインターネット上にあるものを使うことも増えてきました。パート譜がもし売り譜ならば、弦楽器は編成に応じたプルト分の購入を促されます。
翻ってマンドリンの世界はどうでしょうか?
演奏会で使うパート譜を他の楽団から借りてコピーしてそれをそのまま自らの楽団の本番でも使っていないでしょうか?そして使用したパート譜はどのように保管していますか?
楽譜、というハード面だけではありません。楽譜上に存在する明らかにおかしな箇所を深く検証することなく見過ごして演奏していないでしょうか?
同じ音楽なのに1回目と2回目の音やアーティキュレーションが違うことに皆さんはどう対処されていらっしゃるでしょうか? 加えてミスプリントなどによる楽譜の整備にリハーサルの多くの時間を割かれていないでしょうか?
楽譜だけではありません。ご自分の楽器に愛情を注ぐことはもちろんのこと、その楽器を常に最上のコンディションに保っておくためには優れた技術者も必要です。またそのコンディションの良し悪しを判断する箇所はこことここ、といったごく初歩的な知識を皆さんは普段から持っていらっしゃるでしょうか?
そして何より、マンドリンの世界に携わる皆さんは、どのくらい他人の演奏会を聴いているでしょうか?
自分たちの活動の範囲の中で完結していては豊かな感性はなかなか養われません。このような習慣を育てるためにも、お手本にするような演奏が身近にあるような環境を作りましょう。
マンドリンを知らない人たちをも魅了するような説得力を備えたマンドリンオーケストラを育てて、そんな音楽が当たり前と思う若手が1人でも多くなること、その中から世界に通用するようなコンサートマスター(ミストレス)が出てくることも大切です。それは、コンサートマスターはオーケストラにとって特別な存在であり、オーケストラの音楽性を決める大切な要素だからです。
全国の中学、高校の部活動としてのマンドリンクラブから大学のサークルや社会人のオーケストラまで、マンドリン合奏を楽しむ皆さんが、特別名器である必要はない、しかし最低限良く鳴る楽器を常に最上のコンディションで使うこと。
楽譜はきちんと購入、もしくはレンタルする。楽譜はその楽団にとっての財産と考え、そこに掛かる費用は当然と思うこと。そして、他者の演奏会になるべく足を運び刺激を受けたり、新たな発見を得られる環境を作ること。そのような意味での(楽譜の貸し借りではない)情報共有をすることで、マンドリン合奏のレベルが益々向上していくこと。
これが私が今、マンドリン界に感じる「まだ確立されていない何か」の一例です。マンドリン界の次の世代交代に向けて私は上述したようなことを伝えていきたいし、そのためのJSYMOだと思っています。
この度も、NPO法人イエローエンジェルさまからはたいへんありがたいご協力をいただいております。また、サポーターとしてご協力いただいている皆さまと、この演奏会を聴きに会場にお越し下さった皆さま、本当にありがとうございます。
この催し物を開催させるために頑張って下さっている事務担当の皆さん、本当にありがとう!
何よりも手弁当程度の報酬で日本のマンドリン界の未来のためにという使命感を持って知恵を絞り共に頑張ってくれている仲間の講師の皆さんには敬意と感謝しかありません。
この場をお借りしまして、全ての皆さまに感謝の意を申し上げます。
2025年11月3日
ジャパン・スーパーユース・マンドリンオーケストラ(JSYMO)主宰・音楽監督
橘直貴