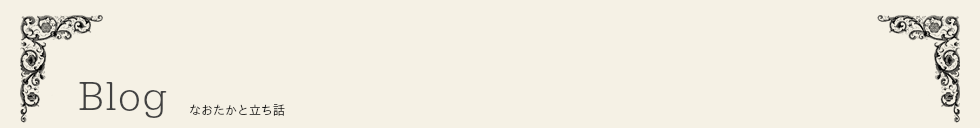一般社団法人日本マンドリン連盟が主催する第29回独奏コンクールの審査員を初めて務めさせていただきました。
6月中旬に応募が締め切られた第一予選では23名の応募者があり、音源(録音)審査が行われました。そしてそれを通過した11名による第二次予選ならびに本選が10月26日(日)かつしかシンフォニーヒルズ アイリスホールで行われました。当日までにやむを得ない事情により2名が棄権されたことはとても残念でした。
第二次予選では課題曲としてL.V.ベートーヴェンの「マンドリンとピアノのためのソナチネWoO43a、WoO44a」が演奏されました。一見シンプルな音楽、譜面ですが、ピッキング主体の演奏法における技術やこの時代の和声、調性による響きの特徴を演奏者自身が感じて表現できるかという、実はとてもハードルの高い課題曲であったと私は感じています。
演奏家である他の審査員の方がおっしゃっておられましたが、ピッキングの音を発する際のピックのストロークが、4分音符なら4分音符、8分音符、もしくは16分音符ならどのように、という響きのイメージを持って発音できていたかどうか。これは、鳴らしてしまえば減衰していくピッキングの音を、会場の残響と対話しながら鳴らした後の時間のことまで想像しながら撥弦できていたかどうかということです。ホールの響きを上手く捉えながら楽器がしっかりと鳴っており、その結果ピアノ伴奏とほどよいバランスが作れていた演奏は、実はそんなに多くはなかった印象でした。
二次審査の末、9名の中から6名の方々が本選に進むことになりました。本選では、ステージへの入場から退場までお一人25分という時間制限を設ける中、第一次の録音審査でもあったG.S.ミラネージの「ラルゴとロンド」が課題曲として、そして自由曲がそれぞれの選択により演奏されました。
私は、このミラネージによる無伴奏の作品が、今回のコンクールの一つのポイントではないかと、このお話をお引き受けして内容を拝見した時から感じていました。というのは、無伴奏の作品、特にこのミラネージは様式感、テンポ感などが試される作品で、上述のベートーヴェンと併せて、個々の演奏者がどのくらいマンドリン音楽以外の周辺の音楽やその歴史を知っているかということが、個々の演奏において露呈してしまうであろうと思っていたからです。
このミラネージについて私見を述べさせていただきますと、作品はタイトルが示す通りレチタティーヴォ風の自由なラルゴと続く即興風のロンドーから成っています。ラルゴ、という音楽用語にとらわれ、ただただ遅く演奏すると、一つ一つの音型同士の関係が希薄になり音楽が止まる。音型の音の配列に従って、冒頭の豊かな重音から一番下の音まで(4小節目)までゼクエンツを伴い下降する。そこまでの音の形が目に見えるような曲線を描きながら、そして見通しを立てながら演奏していた方は、残念ながら見受けられなかったようです。続くロンドーは、 A-B-A-C-A〜のような循環する形式を持った音楽。もちろん一番大事なのはAの音楽、このAを軸として、挿入される次の部分へのキャラクターの橋渡しや場面における曲想の違いをしっかり表現できるかどうかが試されます。キャラクターの違いのみならず、部分と部分を繋ぐ移行の音楽が自然であるかどうか、また時には間をしっかり取れているか、ということもメリハリのある表現に必要とされるところです。
無伴奏の作品はバッハのものが有名です。バッハは正にそうですが、これは欠落による美の音楽です。どういう意味かといいますと、メロディーには伴奏としての和声が全て演奏されるのではありません。無伴奏の作品とはそこで演奏されない和声、つまり欠損している声部を聴いている人の頭の中に想像させる音楽なのです。
それともう一つ、現在のマンドリンの演奏スタイルは楽器も含めて19世紀半ば頃より確立されたもの。だとしても音楽の歴史はもっと長く古いので、そういった音楽をも俯瞰しなくてはいけません。ロンドーに書かれている Allegro Moderatoという表示は、現代の楽典として直訳すると「速く、中庸に(中庸な速さで)」ですが、古い音楽を勉強すればこのような現代の速度に関する表記は、イタリア語としての本来の意味を知らなくてはならないことに気付くでしょう。アレグロは決して速いという意味だけではなく、ある状態を示す言葉、さらにモデラートと付け加えられている場合は速くなくてよい。とするならば、ミラネージのロンドーの部分は弾き飛ばさずにもっとゆっくり、気楽な気分が表現できるように、特に途中から重音が頻発するところの個々の和音がしっかり鳴るテンポを取って全く問題ないということになります。ロンドーは皆さん随分速く弾かれていたので、重音は味わう間もなく通り過ぎて行き余韻も聴き取れない、曲想としても深刻な演奏が殆どでした。その意味ではミラネージ、これなら手放しでよいと思える演奏は、今回私は残念ながら出会うことはできませんでした。
自由曲というのは、個々の演奏者の趣味や好み、時には戦略が見えて面白いものです。これは皆さんがお弾きになりたいものを弾くということで全く問題ないのですが、コンクールですからもし入賞を狙うのであれば不協和音を駆使したテクニカルなものを選ぶのなら上から下までバッチリ完璧に音符を並べて暗譜もして、その上で音楽性や音色が優れていないと上位には行けません。特にこういうものは、圧巻、という言葉がぴったりなくらいな演奏でないといけません。現代的なものばかりではなく、圧倒的な存在感や説得力、これを人は時にオーラといったりもしますが、このようなものを身に纏った人が勝っていくのがコンクールではないでしょうか?
また、伴奏者の善し悪しというのは本当に大切だなと思ったことも追記しておきます。
私自身も指揮者としてこれまで幾つかのコンクールに挑戦して参りました。喜びよりも寧ろ苦労したことの方が多い私のコンクール挑戦の歴史でしたが、そんな自分の経験も交えつつ、今回の審査を務めさせていただき感じたことを率直に書かせていただきました。
ここまで書いたお前がいうな、という感じかも知れませんが、コンクールは水物です。これは自分の経験からもハッキリといえることです。くじ運がもし違っていたら全く違う結果になっていたかも知れませんし、そのことによる演奏者のコンディションも刻々と変化するはずです。誰の次に演奏するかというのはその人の印象を左右する大事な要素です。ですからコンクールは時の運です。今回挑戦して思いが叶わなかった皆さんは、このことでしょげる必要はこれっぽっちもありませんし、その人の音楽性や人間性が否定されたわけでも全くない。挑戦する人には常に門は開いているし、意欲ある限り挑戦するとよいと思います。何故ならばコンクールという目標に向かって人はよく練習し、よく学び、よく緊張もする。そして何よりレパートリーが増えます。
しかしコンクールを取り巻く社会環境として、ある演奏者の音楽性を判断し見極める時に、受賞歴という肩書きにとらわれず、それぞれがよい耳と感性を持ってよい演奏とそうでないものを聴き分けられるようにならないといけません。社会全体の耳を養いよい聴衆、ひいてはよい愛好家を育てること、こちらの方がよほど難しいのではないかと私は常々感じています。何故なら人は、知名度の高さや肩書きに引き摺られてしまうものです。よい仕事をすることと知名度が高いことは一見重なっているように見えますが、実は全く別の次元のお話だと私は思っています。
話が少し脱線して参りましたので、今日はこの辺にさせていただきます。
2025年10月27日
指揮者 橘直貴