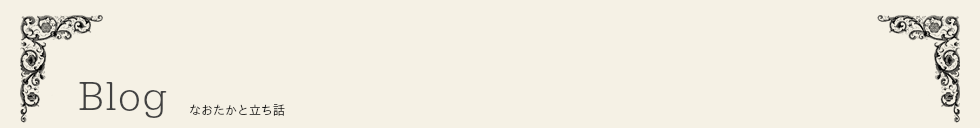今日も「弦楽グループひととき」の演奏会の日がやって参りました。
毎年ほぼこの時期に、こうして皆さまの前で演奏させていただく機会をいただいておりますことをメンバー一同、深く感謝しております。
例年、メンバーの方々からこのプログラムにご挨拶の文章を書いて下さいと依頼されるのですが、毎年同じようなことを書いても仕方がないので、今回は私が今勉強していることややりたいことを少し書いてみたいと思います。
この数ヶ月、私は音楽修辞学勉強会というところに顔を出させていただくようになりました。
以下書きます内容には、習ったばかりの受け売りの部分が多々ありますこと、何卒ご容赦願えたらと思います。
修辞学とは、弁論や叙述におけるある事柄を相手に伝える時のより効果的な技術、またその学問のことです。恐らくその昔、教会などでは、キリスト教の教義を人々に効果的に伝えるためのものとして特に発達したのではないかと思われます。その効果を音楽に置き換えた修辞法が音楽修辞学というものです。
ではそれは一体どういったものか?
音が二つ以上存在し連なり、音の高さの違いや時間的な関係によりリズムが生じます。こうしてできたいくつかの音の連なりのことを音型(フィグーラ)というのですが、個々のフィグーラが示すものには明確な意味がありました。また音に付加されるシャープ、フラットにも十字架、或いは涙という意味があったといわれています。主に歌詞を伴った声楽曲に音楽修辞学は用いられましたが、器楽曲にも同様に使われたようです。仮に上声部にシャープが存在し、逆の下声部にフラットが存在する場合、十字架に架けられたイエス・キリストを母マリアがその下から涙しながら見上げている、そのような情景も音によって示されていると考えることができます。
音型や付加される記号など、それらがある法則に則って配列された場合ある意味を持つ、ということをアフェクトといいます。アフェクトとは、日本語に適当な訳がないのだそうで、近い意味としては情緒、情感、もしくは感情といったものに訳すことが多いようです。つまり、あるフィグーラからもたらされる情緒が体系化され、全部で100程あるといわれているアフェクトが、個々のフィグーラと結び付いて音楽修辞学という学問を形成したのです。
では何故それらの学問がヨーロッパにおいてさえ一度忘れ去られたのでしょうか?
それは、恐らく18世紀後半から19世紀において、作曲において最も重要とされるものが、作曲家個人の独創性ということに変化したからではないかといわれています。フィグーラがある意味を持つという音楽修辞学は、確かに旋律線をある程度決めてしまう可能性をも孕んでいます。主にロマン派の時代以降にある価値観、とりもなおさず私たちが日頃素晴らしいと感じ接しているクラシック音楽の多くは、作曲家の独創性や精神性に近付きたいという欲求の現れでもありましょう。音楽修辞学とは対極にある価値観なのではないか、とも私は思います。
しかしながら、ロマン派のある時期までは、この音楽修辞学という学問を知識として知っていた作曲家がいたであろうことは想像に難くありません。特に、今日演奏致しますブラームスは、過去の作品を深く研究した作曲家の一人でした。過去の遺産の大切さ、素晴らしさを知っていたからこそ、ブラームスはロマン派の時代にあって古典的な書法に拘り、パッサカリアやヴァリエーション(ディヴィジョン)などのいにしえの形式を自分の作品に取り入れ、ひいては当時最も急進的であったヴァーグナーと音楽的価値観において対立したのでありましょう。
ロマン派の時代、いえ、そこから現代に至るまで私たちは、フレーズは長く、歌うように演奏することが求められます。実際に私もそのように習いました。恐るべきことに、ロマン派の時代からの価値観は現代に生きる私たちに受け継がれてきました。しかし、それまでの時代の演奏、また音楽とは、話した言葉が音としてその瞬間から消えていくように、話すように、語るように演奏されました。フレーズはもちろんあるものの、その単位が一つのフレーズの長さに重きを置かれるのではなく、もう一つ小さな音型という単位で考えるということです。
私が心より尊敬するヴィオラ・ダ・ガンバの師匠・神戸愉樹美先生に、ある時私は「端的にバロック音楽とロマン派の音楽の違いは何ですか?」と尋ねてみたところ、先生からは「そうね、語る音楽と歌う音楽の違いじゃないかしら」とのお言葉をいただきました。けだし名言、この言葉に本質が詰まっていると私は深く感じました。
この「語る音楽」というものを、歌う音楽との適正なバランスの中で作っていきたい、それこそが古楽的なアプローチということになります。日々の活動の中で私が最も信頼を置いているヴァイオリニスト・廣末真也さんには「弦楽グループひととき」の今回のシーズンの中でも、数度に渡るたいへん充実した中身の濃いレッスンをしていただきました。この場をお借りして廣末さんに感謝の意をお伝えするのと共に、彼とタッグを組むことで今後も様々な場での語る音楽への実現と追求を続けて参りたいと思います。
もう一つだけ書かせていただきます。
ある音型や記号がアフェクトを表したのと同様に、当時の美術においても同じようなことが為されていました。ある物体が絵画において記号性を帯びていたのです。ご存知の方も多いと思いますが、象徴主義(イコノロジー)というものです。例えば髑髏は人間の死を表し、果物は若さを、そして聖書はもちろん信仰心を表すなど、その一つ一つが意味を持っていました。テーブルの上に物が置かれた静物画で、かじり取られた果物、開いて逆さにされた聖書、髑髏が置かれた絵画にはその寓意として、人の一生を示したものではないかと思われます。そして人々はその絵画を家に飾り日々眺めることで、こうなりませんように、という戒めの気持ちを持って毎日の生活を送ったのではないかと思います。因みに、このような絵には必ずといってよいほど、以下の題名がついています。「ヴァニタス」。それは、無情。人生とは常に無情なもの、ということでありましょう。
困ったことに、私はこの歳になっても他人から学ぶことばかりです。しかし、学ぶことは楽しいもの。今日の演奏会も私の人生を俯瞰してみたときに、大きな大きな勉強の場でありましょう。
それでは、今日も最後までごゆっくりお楽しみ下さい。本日もご来場のほど、誠にありがとうございます。
2017年6月8日
指揮者 橘直貴