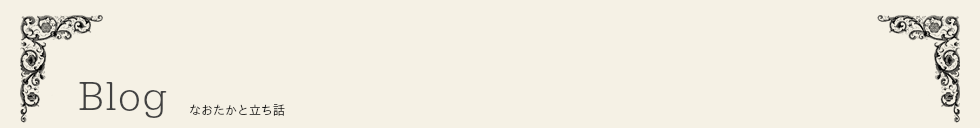〈本日の演奏会について〉
本日の「コンセール・エクラタン福岡 第6回公演 古典派の夜明け〜ナチュラルホルンとガット弦で蘇る当時の響き〜」では、古典派の時代の作品を当時の響きで再現するという試みの演奏会であります。
当時の響きの再現のために弦楽器にはガット弦を用います。ガット弦の響きは、演奏を通じて味わっていただきたいのですが、本公演における響きの探求へのもう一つの大きな鍵となるナチュラルホルン、その魅力についてのお話と演奏を途中に差し挟むことで、皆さまにより楽しんでいただけたらと思いまので、ここではまず「古典派」という言葉についての解説を行なって参りたいと思います。
〈時代の変遷〉
因みに、古典派時代の前は、バロック時代というものでした。この言葉は一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。音楽に限らず全ての芸術のジャンルにおいてバロック様式というのは存在しましたが、今回は音楽のジャンルに限って進めて参ります。
実はバロック時代、古典派時代という言葉の定義はとても難しく、大バッハと呼ばれるヨハン・セバスティアン・バッハの死(1750年)をもってバロック時代の終焉、交響曲の父と呼ばれるハイドンの作品から後を古典派、このようなざっくりとした時代区分によって分けて考えているという傾向があります。しかし厳密にいうとそれは正しくないようです。
歴史をもう少し大きく俯瞰してみたいと思います。バロック時代の前はルネサンス期、更にその前を中世と区別していますが、宗教的な教義が人間の考え方や生活の中心であった中世に対して、その反動から人間性の解放などを目指し、芸術における全ての分野で新たな可能性が模索されたルネサンス期の中で、その音楽の本質ともいえるポリフォニー音楽(多声音楽)が発展をみせます。このルネサンス期の多声音楽を更に発展させつつ細部に多くの装飾を施すことで、バロック時代に入ってからもポリフォニー音楽の様式は深まっていきます。しかし、ルネサンス期の人々から見たそのバロック時代の様式や装飾は、ゴテゴテと過剰なものと感じられ、時に奇をてらったものと映ったようで、そこから「バロック」という名前が生まれ、それは言葉の語源となった「いびつな真珠」というべき不自然さを伴っていたのです。
〈バロック時代と古典派、音楽における違い〉
バロック時代の音楽では、当時の伴奏法の形態である通奏低音の上に全ての要素が構築されていました。伴奏楽器が間断なく演奏し続けることから「バッソ・コンティヌオ」という名が付いたこの通奏低音にはチェロ、ヴィオローネ、チェンバロ、オルガン、リュート(テオルボ)などが用いられました。鍵盤・リュート奏者たちは、音符の上下に書かれた数字付き低音という数字と楽譜を見ながら、作品における肉付けのような和声を即興で演奏していたのですが、古典の作品では変遷と共にその習慣が廃れてきます。何故なのか?例えばバッハが自作を自分の思う通りに演奏してほしいと考え、全ての装飾や音符、通奏低音を用いず伴奏パートさえも楽譜に書き込んだように、作曲家が作品全体に対しての責任を全うする、そのような流れもあるものと思われます。
〈古典派の夜明け〉
もう一つ大きな変化が現れます。それは、多声音楽からメロディーと伴奏というシンプルな形(ホモフォニー音楽)への構造の変化と、作品全体の形式の調和に重きが置かれるという点です。曲中で性格の異なるテーマが複数あり、特徴がより明確なそれらが別々に提示された後、それぞれのテーマは細分化され転調を伴いながら展開され、そして最後にもう一度テーマが再現されるという、ソナタ形式に基づく音楽が生まれます。作品全体への形式美に重きが置かれることと同時に、それを支える和声には機能和声といって、隣り合った和声がある一定の方向性を持って進む法則が見出されます。通奏低音の習慣が廃れた最大の理由はここにあります。
それでは、本日の演奏曲順に従ってそれぞれの作品を解説してみたいと思います。演奏会最初は大バッハの次男C.P.E.バッハが作りましたチェロ協奏曲です。この作品の魅力と解説については、本日のソリストである懸田貴嗣さんに解説をお願いしました。ここで懸田さんにバトンタッチさせていただきます。
本公演では、古典派の時代の響きの再現というテーマの他にも、このような作品全体を覆う均整の取れた美しいプロポーションという視点からもそれぞれの作品を楽しんでいただけることと思います。
それでは、本日の演奏曲順に従ってそれぞれの作品を解説してみたいと思います。演奏会のオープニングを飾る曲は、大バッハの次男カール・フィリップ・エマヌエル・バッハ(C.P.E.バッハ)が作りましたチェロ協奏曲です。この作品の魅力と解説については、本日のソリストである懸田貴嗣さんに解説をお願いしました。ここで懸田さんにバトンタッチさせていただきます。
〈C.P.E.バッハ作曲 チェロ協奏曲〉
かの有名なヨハン・セバスティアン・バッハの息子カール・フィリップ・エマヌエル・バッハ(1714-1788)。今でこそ父親の圧倒的な知名度には劣るものの、少なくとも18世紀の間は、ハンブルクで楽長として活躍した息子エマヌエルのほうがはるかによく知られた存在であった。
エマヌエルは、ハンブルクに移る前の1740年前後から1768年までベルリンのフリードリヒ二世の宮廷で仕えていた。フルートを愛する王フリードリヒは最新のイタリア音楽に熱狂し、当時のヨーロッパでも最も大きい部類に入る楽団を擁していたのだが、エマヌエルは作曲家としてではなく、主に王の演奏における通奏低音を担当する第1チェンバロ奏者として雇用されていた事情もあり、その頃エマヌエルの作品が宮廷で演奏されたという記録はほとんど残っていない。
本日演奏する作品を含めて3曲存在するエマヌエルのチェロ協奏曲は、ベルリン時代の1750年代に作曲されたのだが、当時まだ珍しかったチェロのための協奏曲というジャンルになぜエマヌエルが着手したかは明らかではない。宮廷外のベルリン市民による音楽アカデミーのような場所で演奏された可能性も推測されている。
特殊事情としては、3曲残るチェロ協奏曲のそれぞれに、他の楽器のための協奏曲編曲稿が存在するということがあげられる。また、その3つ(チェロ、チェンバロ、フルート)の稿のうち、どの楽器のための稿がオリジナルであるのかということもいまだにはっきりと確定することはできない。オーケストラ部分は基本的に変更がなく、ソロ・パートのみが、それぞれの楽器の特徴や制限に合わせて、巧みに編曲されている。本日演奏されるイ短調の協奏曲のみが、作曲者本人によるチェロ協奏曲浄書譜が残されており、作曲者の他の事例から、このイ短調協奏曲に関してはチェロ稿がオリジナルである可能性が非常に高いことが分かっている。
〈ナチュラルホルンの魅力〉
懸田さん、ありがとうございました。再び橘が書き進めたいと思います。C.P.E.バッハの演奏の後は、ナチュラルホルンの音色と魅力をトークを交えながら、モーツァルトの「音楽の冗談」の第4楽章の演奏でお楽しみいただきます。
〈交響曲の歴史〉
本公演では交響曲と呼ばれるジャンルから2曲聴いていただきます。この交響曲という言葉はイタリア語におけるSinfoniaを語源とし、これは16世紀末にオペラが誕生して以来、その幕開け前の器楽曲である序曲を指しました。とりわけイタリア風と呼ばれたこの序曲がその後単独で演奏されるようになると、「急-緩-急」という形式が拡大され、後にはそれぞれの部分が一つの楽章として独立します。加えて踊りの要素であるメヌエットが三つ目の楽章として挿入されることにより、交響曲の原型が作られたのは17世紀後半〜18世紀初頭のことです。これと対比される器楽だけの作品として、当時の合奏協奏曲、すなわちConcertoと峻別する必要が生じたといわれています。
〈ハイドン作曲 交響曲第6番「朝」〉
17世後半の交響曲の誕生以来さまざまな管弦楽法が試され、次第に一つのジャンルとして確立されていく中で、ハイドンは生涯において番号なしの作品も含めると106曲もの交響曲を遺してその後の交響曲の礎を築いたことから、交響曲の父と呼ばれるようになりました。本日聴いていただきます第6番「朝」は、この作品を書いた当時仕えていたエステルハージ公から「朝」「昼」「夜」というお題を与えられ書かれた交響曲の一つです。ハイドンの交響曲には副題が付いたものが数多くありますが、副題の中には作品の内容には全く関係がないか、曲中のごく一部に特徴的に出てくるから、というだけのものや、ハイドンの交響曲を聴いた後世の人が名付けられたという例もあり、ハイドンのあずかり知らぬところで副題が付けられたものの方が圧倒的に多いのですが、それは100曲以上あるこれらの作品を覚えやすく整理するのに役立っています。しかしこの「朝」は、その言葉からハイドンがインスピレーションを得て書いたという珍しい経緯があります。
「朝」が、ハイドンの「交響曲」として扱われるようになったのは、比較的最近のことのようです。というのはこの作品は交響曲というよりは合奏協奏曲の様式を取っているからです。先ほど説明しました交響曲と異なるもう一つの重要な器楽曲のジャンルであった合奏協奏曲、つまりConcertoとして、エステルハージ家に仕える宮廷音楽家たちの演奏技術の高さを、ハイドンがその家の主人に誇示したかったということでしょうか?
本日はエクラタンメンバーがどのような魅力溢れる素敵な独奏を聴かせてくれるのか、目で見て、耳で音を感じていただき、演奏を楽しんでいただけたらと思います。
〈モーツァルト作曲 交響曲第40番〉
交響曲第40番ト短調。これはモーツァルトが最後に書いた三大交響曲と呼ばれる第39番~41番の一つです。モーツァルトが亡くなる3年前、1788年の夏に、この三つの交響曲は一気に書き上げられました(第40番には1788年7月25日という日付が書かれている)。モーツァルトがその生涯を通じて首尾一貫していた作曲における態度とは、依頼がなければその作品を決して書かなかったということです。どんなに作曲の筆が捗っていた作品でも、演奏の機会が失われてしまった作品について、モーツァルトはあっさりと筆を折ってしまうという徹底したプロフェッショナルな職人気質を持っていました。ところがこの三つの交響曲は、誰からの依頼もなく書かれた作品たちでありました。これは一体何を意味するのでしょうか?
別の角度からこの頃のモーツァルトを眺めてみましょう。映画「アマデウス」などで表されているような、モーツァルトの晩年が、生活がとても困窮し共同墓地にも葬られた、というエピソードは実は真実とは多少異なります。彼は作曲やお弟子さんへのレッスンにより相当な稼ぎを得ていましたが、一方で宮廷に出入りをし、そこで仕事の依頼を得るための遊興費用が莫大であったともいわれています。フランスのパリでは翌年フランス革命が起きますが、ハプスブルク帝国の都・ウィーンにおいても封建社会の終焉と一般市民たちの台頭の予感を、モーツァルトは時代の空気として敏感に感じ取っていたのではないでしょうか?そのような時代の流れの中で、現在の演奏会の原型となる演奏会も生まれます。それは予約演奏会と呼ばれました。演奏を聴きたい一般市民たち、とりわけお金持ちの商人たちがお金を積み立てて予約演奏会を開くのです。モーツァルトのための予約演奏会が彼の生前一度行われたという記録が残っています。
三つの交響曲を引っさげて、モーツァルトはもしかしたら予約演奏会に呼ばれることを期待していたのかも知れません。それは分かっていませんが、確実にいえることは、モーツァルトは三つの交響曲を一つの大きな作品と捉えていた節があり、実際には音楽としてもそのような構造、調的な関係にもなっています。当時の記録を辿ると、1788年モーツァルトはロンドンに行く予定があったようです。結局実現しなかったその旅行がどのような目的であったのかというのは、同じ頃ハイドンがロンドンに住んでいたヨハン・ペーター・ザロモンというヴァイオリニストであり興行主からの依頼を受けてザロモン・セット(交響曲第93~98番)といわれる作品群を依頼され多額の報酬を得たのと同じように、ロンドンに行き、三つの交響曲を高く買ってくれる人間との接触を試みようとしたのではないかと思われます。同時に、当時ドイツにあったプライトコプフ ・ウント・ヘルテル社という出版社にこれらの交響曲を売るということも考えていたようです。
三大交響曲はどれもモーツァルトの生前、演奏されたという記録がないために、私たちもその記録を信じるしかないようです。しかし本公演で演奏するする第40番は初稿版(第1稿)といわれるもので、それは通常演奏されることの多いこの作品のオーケストレーションからクラリネットが除かれたものです。更に第2楽章の一部分は全く違うオーケストレーションが施されており、本日はこれを含む第1稿:第3段階というバージョンで演奏します。
何らかの理由によりロンドン行きが実現しなかった翌1789年に、モーツァルトはドレスデンとライプツィヒへ、更に1790年にはフランクフルトとマインツというドイツの各都市を訪れています。上述したように、彼は演奏する機会がなければこのような書き直しは決してしなかったはず。となれば、少なくともこの第40番に関してはモーツァルトが生前演奏した確率が高いのではないか、という推理をすることができます。
三つの交響曲を一つの大きな作品と考えていたモーツァルトが、この第40番を彼の中でも珍しい短調、とりわけ哀しみを表現するのに相応しいと考えられていたト短調を使って書いたことを、本公演におけるガット弦による弦楽器の響き、ナチュラルホルンや木管楽器の純正な響きによって、モーツァルトのこの偉大な作品における謎を解き明かしてくれるのではないかと期待が膨らむばかりです。最後までごゆっくりお聴き下さい。
2018年7月27日
文責 橘直貴 懸田貴嗣
校正 廣末真也 松隈聡子 松本優哉