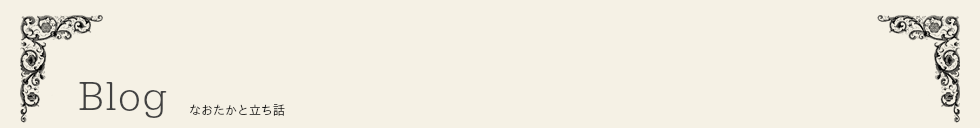フィラルモニカ・マンドリーニ・アルバ・サッポロ演奏会2020に寄せて
本日の演奏会をより深くお楽しみいただけるよう、
いくつかの考察を書いて参ります。
①「オーケストラの配置について」
マンドリン合奏の呼称をここでは便宜的にマンドリンオーケストラとして話を進めたいと思います。また、ヴァイオリンなどのオーケストラと対比させる意味で、そちらはシンフォニーオーケストラとして話を進めて参ります。
シンフォニーオーケストラには1st.ヴァイオリン、2nd.ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバスがあります。対してマンドリンオーケストラの方は1st.マンドリン、2nd.マンドリン、マンドラテノーレ(マンドラ)、マンドロンチェロ(チェロ)、マンドローネというのがマンドリン属といわれる楽器、これにギターとコントラバスが入ることが現代における通常の編成です。
弦を擦って音を出すコントラバスが何故入るのか?というのは、例えば吹奏楽にコントラバスが入ることでチューバの低音をコントラバスにより補強し、響き全体をより豊かにするという意味合いと同類のものだと思われます。但し、マンドリンオーケストラ特有の事情としては、マンドローネという楽器が一般的ではなく所有している人が少ない、調弦の仕方もマンドリン属の楽器と違っており、楽器同士の互換性が薄いということもあるようです。これはシンフォニーオーケストラにおけるチェロとコントラバスの関係に似ております。マンドローネの音域も、合奏の最低音域を担うには楽器としてやや中途半端なようです。
ところでこのオーケストラにおける配置ですが、これはシンフォニーオーケストラに限らずマンドリンオーケストラにおいても、我々演奏者の頭を常に悩ませる問題です。というのは、どの配置においても必ず得るものと失うものが存在するからです。
シンフォニーオーケストラとマンドリンオーケストラは、元来、比較してどちらかを元に考えることは必ずしも正しくはありませんが、それぞれのオーケストラにおける各楽器の配置は、会場の響きや演奏者の求める演奏スタイル、何よりも演奏者同士が演奏しやすいかどうか、などの諸々の条件で決めるものですが、シンフォニーオーケストラでは長らく、(図1)のような配置が取られて参りました。これは下手から上手に向かって高い音域の楽器から低い音域の楽器を順に配置するというものです。作品や会場の響きによっては、ヴィオラとチェロを入れ替えて、チェロを内側に配置することでチェロの響きが客席側により届くようにするということも行われます。
ところが最近では、作品の書かれた当時はこうだったのではないかという想定のもとに、ヴァイオリンのふたパートを両翼に配置する対向配置というものも一般的になりつつあります。ご参考までにこれを(図2)で示しておきます。
この対向配置は、別名古典配置といわれるもので、基本的には同じことをやっているものを分ける、という考え方です。つまり、旋律を担当することの多い1st.ヴァイオリンと2nd.ヴァイオリンを対向させることで、ヴァイオリンの響きが両側から聴こえてくるというもの。聴く側にとっては聴いていて楽しいこの配置は、実は演奏者にとってはあまりありがたくないのです。特に2nd.ヴァイオリンにとっては、寄り添うべき旋律の1stが物理的に離れてしまい聴こえにくい、結果演奏しにくいというデメリットが生じてしまいます。
ここからマンドリンオーケストラの話になりますが、私は以前からマンドリンオーケストラにおいて、1st.マンドリンがトレモロ奏法で旋律を弾いている場合、いわゆる内声と呼ばれる2nd.マンドリン、マンドラ、チェロの響きをかき消してしまうことがとても気になっておりました。特にそれは内声がピッキング奏法によって細かなパッセージを演奏している場合に顕著でした。その際私の耳には、全体を塗りつぶしたような演奏に聴こえてしまうのです。
マンドリンオーケストラもシンフォニーオーケストラと同様に、舞台下手より1st.マンドリン、2nd.マンドリン、マンドラ、チェロ、ギター、そしてその上手後方にコントラバスという配置で行うのが一般的です。実際にアルバとしても昨シーズンまではこの配置で行って参りました。しかし、今回は工夫と試みとしまして、内声を浮き立たせ、その上で音域の高い旋律もきちんと聴こえることを意図しました。そこで、(図3)のような配置を試みてみました。
音域の高い音は、客席に届きやすいということもあり、音響学的にも奥まることを覚悟の上で1st.マンドリンをステージ中心に移動させました。そして、マンドラという楽器は、シンフォニーオーケストラにおけるヴィオラとは若干違う役割を与えられているので、マンドリンオーケストラにおける第二の旋律楽器ともいえるマンドラを、下手の一番聴こえるであろう位置に配置しました。また全ての楽器の表面にはサウンドホールという穴があいており、本体で共鳴した響きはこの穴を通って響いていくのですが、2nd.マンドリンは、一番上手に位置することにより、彼らの楽器のサウンドホールは自然と1st.側を向くことになります。このことは1st.マンドリンに2nd.マンドリン音を聴きやすくするメリットがある反面、楽器の表板が客席とは反対方向を向いてしまうため2nd.マンドリンが聴こえにくいとうリスクに晒されます。また、どこのマンドリンオーケストラにおいてもなかなか聴こえにくいギターを今回は二群に分けて、ほぼ中心に配置しました。その理由は、マンドリンオーケストラにおいて和声的な要素を担うとても大切なギターの響きを全てのパートが感じながら演奏できるように、という狙いです。但しここにもギターの演奏者の方々には、奏者がが離れ離れになることでアンサンブルしにくいというデメリットが生じます。
得るもの、失うものの中で、何に妥協しどこを取るか?常にそのせめぎ合いの中で、今回のこのオーケストラの配置をお聴きの皆さまにはどのように感じられるのか、受け取られたのか、その賛否も含めて是非ご意見をお聞かせいただければと思います。
②「二橋潤一氏のプレクトルシンフォニーについて」
二橋潤一氏は、マンドリン、ギターのソロ作品、合奏作品を数多く作曲されている日本を代表する作曲家の一人です。二橋氏のマンドリン合奏における作品は、各団体から委嘱を受けて書かれることが常であり、このプレクトルシンフォニーも広島女学院中学校・高等学校の第30回の記念定期演奏会における委嘱によって書かれました。
二橋氏はこのプレクトルシンフォニーを書くにあたり、当時クラブの顧問の先生であった松重正清氏のお名前、MATSUSHIGEからドイツ語による音名として読み替えが可能な、A、S(ESとして読み替える)、S、H、G、Eをピックアップ、これらを音に置き換えてこの作品全体を貫くテーマと致しました。この音の配列を楽譜にしたものを(譜例1)に示します。このように、作曲者によるユーモアとウィットに富んだ音の遊びは、歴史的にもよく試みられたことです。
しかしこれを遊びでなはなく、学問として真剣に音と言葉を結び付けていた時代というのもありました。例えば皆さんもよくご存知のバッハという作曲家ですが、自身の名前BACHの文字は、BはAを1とすると2、Aは1、Cは3、Hは8ということになりますが、これらを全て足すと14です。この14という数字を作品の各所に当て嵌めました。因みに、バッハというのは苗字ですが、名前のヨハン・セバスチャンのJとSを先程の14に足すと41となります。この14、41というシンメトリーをバッハは調和の取れたものの象徴と考えたようです。その他にも数字が音として象徴されている主なものを一例ですが挙げておきましょう。3は聖なる三角形、そして三位一体を表し、4は東西南北、また空気、火、水、大地の世界を構成する四つの要素、5は五つの傷を負ったキリストを表すことから人間の象徴、10は十戒による神の掟、12は12使徒に象徴される如く教会を表します。このような概念は数象徴と呼ばれて他にもたくさん種類があり、最も数象徴を多く使って作曲をした人がバッハといわれます。音符の数や主要テーマとなるモティーフに数字を関連させたりと、一見知らなければそのことは闇に葬られてしまうような作曲家による最高度の遊び、二橋氏のプレクトルシンフォニーには、このような価値観に通じるものがあるのではないでしょうか?
因みに、何故このような価値観が西洋の歴史において失われていったのかということは非常に興味深いことです。バッハの生きていたバロック時代というのは、語る音楽の時代でした。音型が言葉そのものを表すことで、身分社会であった当時は高度な知識層の人々というのが存在し、音楽を聴けばそこで表現されている内容や情感(アフェクト、といいます)が即座に理解できた、といわれています。ところがロマン派の時代になり、歌う音楽になると旋律線は可能な限り長く朗々と演奏することに重きが置かれ、各音型よりもその旋律線そのものが、例えばこの旋律自体が憧れの人を表す、などのより漠然としたものになります。これは、音楽と文学との結び付きが、時代の流れと共に強まったことが大きいのではないかと私は考えています。またフランス革命後、身分社会が表向きは崩れていき、教育というものが下の階層の人々にも行き渡るようになった結果、誰にでも分かる音楽を、というように社会の価値観が音楽においてそのような形でも変化したのかも知れません。もう一つ、決して見逃せない価値観の変化は、フランス革命の時代に生きたベートーヴェンあたりから、作曲家やそれらの人々が生み出す作品の価値というのは、その人の独自性や個性、独創的なアイディアに最大限の重きが置かれるようになりました。このことも実は語る音楽から歌う音楽に変わってしまった一つの要因ではないかと私は考えています。
恐らく北海道の皆さまの耳には、本日初めて聴かれるであろうこの二橋氏のプレクトルシンフォニー、ただ知識がないままに耳にするのと、そのような裏話を知っていただいて聴いていただくのでは自ずと親しみ方も違ってくることのように思われますので、今日はこちらに書かせていただきました。実際の演奏の前にも少し解説を入れさせていただきますが、上述したことを延々とお話ししますと退屈だなと感じられたしまう方々もいらっしゃると思い、今回は敢えてご挨拶文ではなく、考察という形を取らせていただきました。
最後までごゆっくりお聴き下さい。
2020年2月29日
指揮者 橘直貴