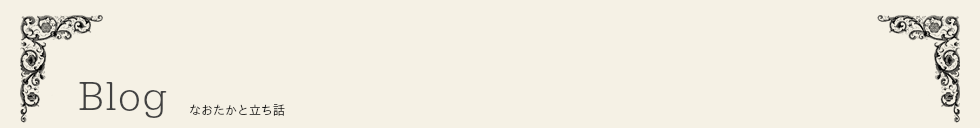「はじめに」
新日響の皆さまへ
こんにちは。世界中を暗く覆うこの新型コロナウィルスの事態、2020年の新年を迎えたあの頃、今の世の中を一体誰が予測できたでしょうか?
先行きの見えない状況が続く中、在宅での自粛、また生活の激変を強いられている方も多いのではないでしょうか?
何よりも新日響にとっては4月に予定されていた演奏会が中止になってしまったこと、皆さまにとって残念で無念で、悔しくやるせない思いをされたのではないでしょうか。その心中をお察しするに余りあります。
この数ヶ月、自宅にて過ごすことが多くなられた方が大半であろうかと思います。そんな皆さまに向けて、次回の演奏会についてより多くの興味を持っていただけるよう、さまざまな資料を基にしながら僕の方から作品に対する考察を語って参りたいと思います。
「ブルックナーの交響曲第9番」
CDというメディアが出たての頃、僕は中学から高校という多感な時期を過ごしていました。部屋を暗くして一人オーディオの前にうずくまり演奏に耳を傾け涙する、そんな橘少年の部屋に頻繁に鳴り響いてた音楽こそがブルックナーの交響曲第9番であり、マーラーの交響曲第9番でもありました。その時から僕にとっての「第九」とは、ベートーヴェンのものは確かに偉大だと思いつつも、ブルックナーでありマーラーのそれでありました。
満を持して今回新日響の皆さまとブルックナーの交響曲第9番ができること、僕自身とても楽しみにして参りました。
多くの曲目解説書にも書かれているように、白鳥という鳥はその死の間際に一度たいへん美しい声で鳴くのだそうで、そのことから作曲家の死の直前の作品を「白鳥の歌」と表現することが多いのですが、数ある白鳥の歌の中でもブルックナーのこの作品はひときわ美しい白鳥の歌と断言してもよいと僕は思っていますし、正に白鳥の歌に相応しい終わり方で曲が締めくくられます。
この作品において常に議論の的となる、残されたフィナーレの断片、これはブルックナーは命の続く限り通常の交響曲のようにフィナーレを書き第9番を4楽章の構成にすることを考えていたようですが、僕にはこの作品が第3楽章のアダージョで終えることを彼自身が覚悟をして書いたのではないかと思えるのです。
多くの方々が述べておられるように、ブルックナーは信仰深い人間であり、常に神は善であって、人間のなすこと全てが神の栄光を反映することでなくてはならない、と考えていたことは間違いありません。つまり、ブルックナーにとって音楽とは神を讃えるためのものであり、この点、同時代を生きたユダヤ人でありながらキリスト教に改宗し結局どの宗教にも入り込めなかったマーラーとの一番の違いであろうと思います。
では、ブルックナーは実際どんな人物であったのかというと、当時のウィーンの多くの人々は「一種の純真な愚か者」とみなしていたようです。具体的にいいますと、単純な人間であり信じられないほどの無邪気な田舎者であったそうです。頭を丸く刈り込み田舎丸出しの方言を使って喋り、何事にも彼よりもはるかによく知っている偉い都会人というものを常に恐れて生活していた、との記述があります。
「版の問題」
以上のブルックナーの人柄、性格を前提にお読みいただければと思うのですが、今回取り上げる交響曲第9番は、そもそも完成していないので、改訂の問題というものは生じません。ノヴァーク版の後に、新たな資料が発見されてその要素も取り込んでベンヤミン・グンナー・コールスによって2000年に新たに校訂され出されたもの、これを今回私たちは使用します。
ただ、ブルックナーを取り上げる際に必ずつきまとう版の問題についてごく簡単に解説しておきます。とはいえ長くなりますので、その先に飛ばしていただいても構いません。
ブルックナーは自分の作品を何とかして演奏してもらいたいとの一心から、指揮者が作品に手を入れたり短縮したりすることに一切口を挟みませんでした。
では具体的に、その時どのような改変が行われたかというのは、管弦楽法の修正、粗野な繋がりを持つ和声の円滑化です。当時のフランツ・シャルクやフェルディナンド・レーヴェといった“善意”を持った指揮者がブルックナーを「助ける」ことを決めたのです。ですので、ブルックナーの場合初版というのは、このレーヴェ版というのを指すことが大半です。
ブルックナーの死から33年後の1929年に国際ブルックナー協会が設立されたことによってローベルト・ハース、またアルフレート・オーレルという音楽学者によってブルックナーが本当に書いた部分を再現し、22巻に及ぶ第一次全集が1932年までに発行されました。これがいわゆるハース版といわれるものです。
1951年にはレオポルド・ノヴァークによる校訂を受けた第二次全集が出されます。これはハース版とは解釈において異なった結論に達することがあったため両方が現在までも存在し、ハース版、ノヴァーク版として原典に忠実な指揮者はこのどちらかを選択することが多いのです。
「実際の演奏に向けて」
さて、話を元に戻します。ブルックナーの生きていた当時ウィーン随一の音楽批評家であったマックス・グラーフは、ブルックナーについて次のように書いています。
少し長いですが、全文掲載します。
「神聖な遺産であるかのようにブルックナーから我々に伝えられたゼヒター(ウィーンにてブルックナーに和声と対位法を教えたといわれるシモン・ゼヒター)の理論は、二つの強靭な柱の上に建てられている。ブルックナーが最も尊敬したのは、深淵の影のような和声に随行する、低声部の精神世界である根音バスの理論と、和声進行の美学を形成する自然和声の理論であった。至るところに法と秩序があり、神聖ささえあった。ブルックナーが譜表の最下段に必ず記した低声の根音進行は、宇宙的な重要性を持っていた。このように、我々はブルックナー和声の偉大さ、そして時にはその堅固さと厳粛さとを理解した。和声の建築家ゼヒターの弟子だったブルックナーは、中世の建築家がゴシックの大聖堂の原型を考えたのと同様に、和声と和声連係について熟考した。こうした道を通って、彼は神の王国へと歩んだのであった」
このように、和声進行はブルックナーの音楽において最も根幹をなすべきものです。また、諸井誠さんなど多くの方々が書いておられるように、同時代を生きたマーラーよりも、その和声の構造は時代を先取りしていたことには間違いがないと僕も思います。
昨年のレクチャーでもお話しましたように、和声を伴った旋律は、必ずカデンツ(終止)に向かいます。ヴァーグナーをはじめとするロマン派後期以降の時代に起こったことを僕なりの言葉で説明すると、終止が引き延ばされて構造が複雑化する、また終止がより曖昧になる。
例えば、元来導音は主音に行く(解決する)などの簡潔な規則や法則があったのですが、それが回避されるようになることで終止感がより曖昧になり、フレーズはより引き延ばされる。結果、和声は多重化され不協和音となり絶えず押し寄せるように聴こえるのです。益々曖昧になった和声はやがて調性の崩壊に繋がる、というように考えていただければよろしいかと思います。そう、12音音階の世界に踏み出していくのです。
不協和音がもたらす感情は、不安や怖れといったものでしょう。対して協和音は、ストレスからの解放、安寧や安らぎ。あまりにも当たり前で単純な解釈かも知れませんが、僕にはそのように思えます。人は常にストレスから解放されることを望んでいます。終止感があった時に、人はそれまでのものの終わりを感じます。終わりを感じるということは、次のものの始まりを同時に感じるということです。こうして私たちはフレーズというものを認識します。
ですから今回、僕が自らの音楽体験をも踏まえつつブルックナーの交響曲第9番について、いつも以上に新日響の皆さんと作り上げたいことの一つとして、不協和音から協和音に到達した時の美しい瞬間、また和声の持つ緊張から弛緩への道筋を味わいたいと思います。不協和音があってこそ、その後の協和音によって私たち演奏者や聴衆もそこに神の姿を見るのです。
「第3楽章と未完に終わった第4楽章」
最初の方に、僕はこの作品をブルックナーの白鳥の歌、と書きました。この白鳥の歌とは、正にこの第3楽章のことを指していると考えても間違いではないでしょう。教鞭を取っていたウィーン大学での講義においてブルックナー自身はこの楽章のことを「演奏するたびにいつも心が揺さぶられる」、「私が作曲したものの中でもっとも美しいもの」と呼んでいたようです。
僕が音楽を読む時にいつも注視する(好きな)、音型によるアフェクト(情感)における考察(音楽修辞学)がありますが、これは譜例が必要になりますので、リハーサルの時などに楽譜をお持ちして少しだけ説明させていただきたいと思います。例えば、第3楽章冒頭の第1ヴァイオリンの短9度の跳躍進行が何を示しているか、などです。3小節目の第2ヴァイオリンとヴァーグナーチューバによって奏でられる音型、また木管楽器の6小節目の上行音型にもきちんと意味があります。
最後になりますが、未完に終わった第4楽章についても少し触れておきたいと思います。第3楽章で終わることを想定したかのよう、とやはり僕は最初の方に書きましたが、ブルックナーは生涯を通じて神に捧げる音楽を同工異曲で創り上げた、という論調にも賛同致します。だとしたら、ブルックナーがこの作品だけをアダージョで終わらせようと思っていたとは考えにくい。ただ、実際にベートーヴェンに始まる9という数字の迷信により書くことを恐れていたことは事実のようです。
ということで、第4楽章の断片をつなぎ合わせて完全な4楽章の作品として演奏するということも行われています。第3楽章が完成した1894年、前述の大学の講義の際にブルックナーは、この作品が未完に終わった際は自分のテ・デウムを演奏して欲しいと語ったことは有名な話ですが、テ・デウムを交響曲第9番のフィナーレとして演奏することは、さまざまな理由により僕はそのようなことはすべきではないと考えます。では、それを語ったブルックナーの本意、意図は何だったのでしょう?それは、ブルックナーは本来この第4楽章、フィナーレで神を称える讃歌を書こうとしていたということに尽きるのではないでしょうか。
ブルックナーが残したフィナーレの断片を補筆して完成したものは、ギャラガン完成版(1983年)、サマーレ=マッツーカ版(1986年)、ヨゼフソン版(1992年)、SMPC完成版(1992/1996年)、コールス完成版(2004/2008/2011年)、ギャラガン完成版(2006/2010年)、シャラー完成版(2016/2018年)など、いくつもあるようです。僕自身は現時点で全てを聴いたことはありません。しかし、この作品に対する人々の興味の大きさが分かりますね。
私たちとして共有しておきたいのは、2002年のザルツブルク音楽祭でアーノンクールとウィーンフィルがレクチャー形式で遺された断片を演奏した記録があるものです。これは僕がCDを所蔵していますので、後ほど皆さまと共有します。また、第1〜3楽章のオススメの演奏ですが、アーノンクールのものはもちろん僕にとって常にとても大きな影響を及ぼすものですが、この第9番については思い入れが強すぎて一つに選ぶことができません。どの演奏も良さがありますし味わいがあります。
参考までに僕が持っている音源は、前述のアーノンクールのものの他に、ハイティンクとコンセルトヘボウ、シューリヒトとウィーンフィルのものです。どの演奏にも共通していることを僕なりに考えてみましたが、金管楽器が荘厳な響きを奏でつつも決して響きが破綻していない、つまり荒っぽくない演奏ということになろうかと思います。
長々と書いて参りましたが、新日響の皆さんと共に、この作品の素晴らしさと本質に楽しみつつ迫って参りたいと思います。シューベルトの未完成との「未完成プログラム」、とても素敵だと僕は感じています。往々にして完全無欠なものに私たちは憧れますが、一方で何かが欠けているからこそ、そこに想像力が働き、あるものの中からないものを頭の中で構築する、そのような作業ができるのも人間ならではのことでしょう。未完成であるからこそ美しく愛おしい、これって、そのまま私たち人間のことではないのかな、と僕などは時折思ってしまいますが、皆さまは如何お感じになりますか?
新型コロナウィルスの事態が終息に向かいこの演奏会が開催できて、皆さまとリハーサルでお目に掛かれることを心待ちにしています。
2020年5月16日
指揮者 橘直貴
【補足】
シューベルトのオススメはブリュッヘンと18世紀オーケストラの演奏がよいと思います。